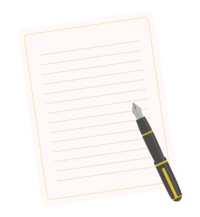
広島県福山市の相続登記・成年後見は佐藤正和司法書士・行政書士事務所へ!
司法書士・行政書士の佐藤正和です。
お亡くなりになった方の遺言書で相続登記を進めるケースがあります。
今回は、その遺言が有効かどうかについて触れさせていただきます。
遺言書、よく見られるのが
①亡くなった方が自ら作成した遺言書(「自筆証書遺言」(じひつ しょうしょ ゆいごん))
②公証人の先生が遺言者から要望を聞き取り作成した遺言(公正証書遺言「こうせいしょうしょ ゆいごん」)
の2種類です(他にも「秘密証書遺言」があります。この記事では割愛します)。
②公正証書遺言については過去に公正証書遺言の有効性が問題となり裁判で争われたケースはありますが、私の経験に限れば、形式の不備等で有効性が問題となる事案に遭遇したことは今までありませんでした。
これに対して①自筆証書遺言については、有効とはいえない遺言書と出合ったのは一度や二度どころではありません。
たとえば、
・作成日付が書かれていない
・「Aに土地をまかせる」など所有権を移す意味なのかが分からない
というものがありました。
公正証書遺言のかたちで公証人の先生に関与してもらうのであれば、曖昧な表現を用いて遺言書ができあがることは考えにくいです。
遺言書作成の相談を受けたのが司法書士でも、司法書士は形式上の不備等がないように遺言で用いる表現には注意を払います。
①自筆証書遺言は②公正証書遺言と比べてお金があまりかからず、しかも誰のチェックも経ずに作成できる点で手軽さがあります。
その反面、有効っぽい遺言書ができてしまうのが怖いところです。
例として子が多くおられる方が自筆証書遺言を残されたとしましょう。
その遺言書に「遺言者が有する一切の不動産を長男Aに託す(たくす)」と書かれていたとします。
「託す」とはどういうことでしょう?
長男Aに不動産の所有権を移すと読み取るのが常識だろうと考える方もおられるかもしれません。
その一方、不動産の所有権移転ではなく管理をさせる(固定資産税を支払う・草刈りなど)という意味だと捉えるのも常識外れだとも思えません。
そもそも特定の相続人に所有権を移す意図であれば、端的に「相続させる」という表現を使うのが(私の感覚では)普通な気がします。
「託す」という表現の遺言書で相続登記をするのはかなり苦しいです。
類似の事案に私は遭遇したことがあり、その節は折角残された遺言を有効なものとして活用できないか思案しました。
色々な資料(詳細は控えます)を添えたうえ、その事案の遺言書の「託す」という言葉に関しては所有権を移転させるという意味を読み取れるのではないかと法務局に意見を求めました。
しかし、残念ながらそのような読み取りは認めてもらえませんでした。
仮にその遺言が有効であれば、他の法定相続人に実印を書類に押してもらうことなく相続登記を済ませることができた事案でした。
しかし、上記のとおり遺言書を活用できなかったため、人数が多い法定相続人全員の遺産分割協議(話合い)、押印手続きなどの協力を得てようやく相続登記は完了しました。
もし協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停の手続きを利用してもらう流れになったと振り返ります。
最近では、「遺言書は自分で作れる」とうたうマニュアル本などがたくさん販売されています。今後はAIを活用する遺言サービスも出てくるでしょう。
遺言書を間違いなく作成できる自信があればそのようなツールを利用するのも良いと思います。
しかし、言葉選びなど自己流にアレンジしようという気持ちが湧くときには、気づかないまま落とし穴を掘ることになるかもしれません。
その穴に落ちてしまうのは、遺言を残す方、その相続人にあたる方、遺言書で財産を受け取るとされた方だと私は考えています。
以上、手軽さには裏があるかもしれないという記事でした。
ブログ記事は業務の参考として作成しております。内容に関し一切の責任を負いかねますのでご自身の責任でご利用ください。
本ブログの文章は著作権により保護されています。無断での使用は堅くお断りします。
☆ブログランキングに参加中☆
![]()
にほんブログ村
↑クリックしていただけるととてもうれしいです!
<失敗しない遺言のためにできること>
広島県福山市駅家町大字万能倉734番地4-2-A
佐藤正和司法書士・行政書士事務所
TEL084-994-0454
お問い合わせはこちら!